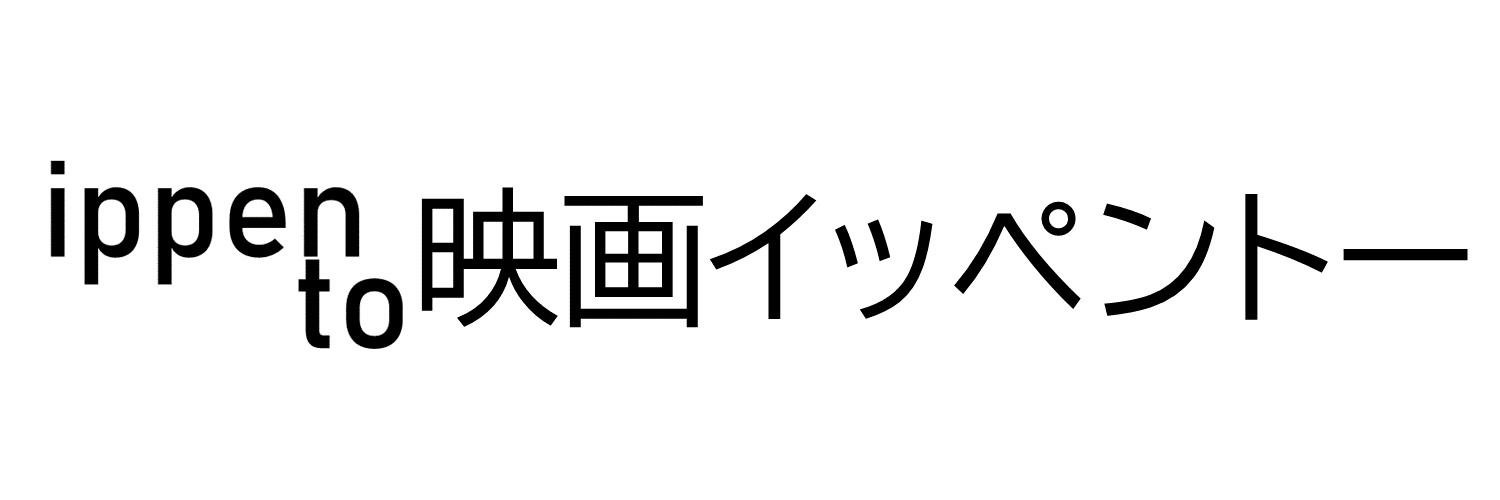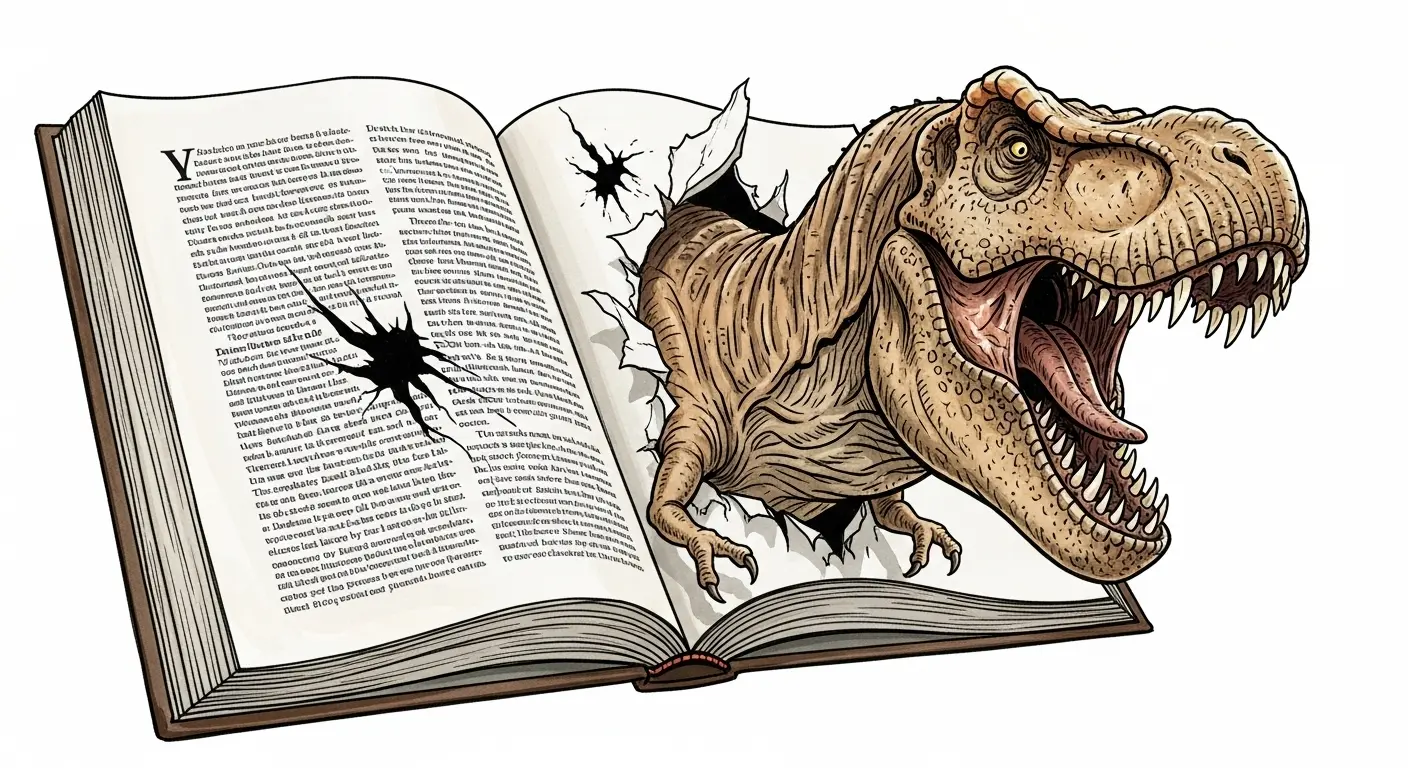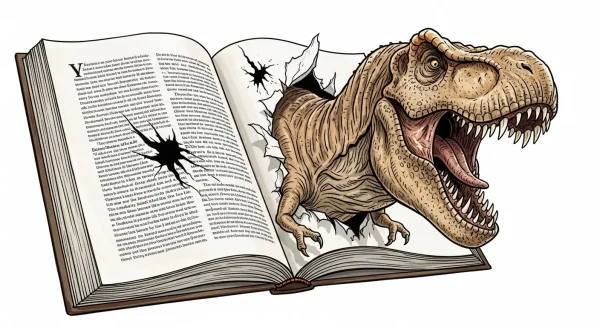
『ジュラシック・パーク』は、恐竜を復活させるという大胆なアイデアと、テーマパークという現代的な舞台設定が融合した作品である。この組み合わせは娯楽作品として非常に魅力的だが、マイケル・クライトンがこの物語を選んだ背景には、いくつかの明確な動機がある。彼は科学技術と人間社会の関係に強い関心を持ち、それを物語の形で表現することを一貫して試みていた。(関連記事:「『ジュラシック・パーク』歴代監督を徹底解説:演出の違いと脚本家とのタッグが生んだ進化の系譜」)
子ども時代からの“恐竜愛”
クライトンは幼少期から恐竜に興味を持っていた。博物館で化石を見るのが好きで、古生物学に関心を抱いていた。この個人的な興味は、後の創作活動にも影響を与える。彼の頭の中には早い段階から、「恐竜を現代に蘇らせる」という構想が存在していた。
実際の執筆活動に関しては、娘が生まれた頃に始まりました。当時は恐竜のぬいぐるみばかりだったので、たくさん買ってしまいました。…ある時点で、恐竜の何が私をこれほど魅了するのか、なぜ恐竜が子供時代と深く結びついているのか、疑問に思い始めました。そして、そうした疑問のいくつかがこの本に反映されています。
出典:Beyond Jurassic Park interview | Jurassic Park Wiki | Fandom 2025年8月4日閲覧
(In terms of the actual writing, it occurred around the time my daughter was born and then I bought a lot of stuffed toys, and they were all dinosaurs because that was what was available at that time…I had to begin to wonder, at some point, what it was about dinosaurs that fascinated me so much or why I thought that they were so tied to childhood. And some of those concerns found their way into the book.)
クライトンはこのように、自身の無意識的な“恐竜への執着”に気づき、それが物語創作の動機になったと語っている。
最初の構想は「少年が恐竜を作る話」だった
クライトンが最初に考えていたのは、少年や若い研究者が恐竜のクローンを作るという物語だった。しかしこの案は、物語としての説得力や読者の共感性が弱いとされ、のちに大幅に再構成された。
私は若い大学院生が遺伝子操作によって化石から一頭の恐竜を作り出すという設定の脚本を書いていたんです。でも、脚本はうまくいきませんでした。
出典:Beyond Jurassic Park interview | Jurassic Park Wiki | Fandom 2025年8月4日閲覧
(I had done a screenplay about a young graduate student who genetically engineered a single dinosaur from fossil remains. And the screenplay didn’t work out.)
また、小説初稿では子ども視点で描こうとしたが、それも却下された。
ついに読者の一人が、子供の視点ではなく大人の視点で書いてほしいと言い、…そこで私は大人の物語として書き直しました。すると皆が気に入ってくれたのです。
出典:Jurassic Park Novel by Michael Crichton – JPT 2025年8月4日閲覧
(Finally one of the readers said that they were irritated with the story because they wanted it to be from an adult point of view, not a kid point of view…So I rewrote it as an adult story. And then everybody liked it.)
このように、初期構想は子どもや若者を主人公に据えた小さな物語だったが、読者のフィードバックを受け、大人の視点で描かれる社会的・倫理的な物語へと進化していった。
科学技術と倫理への警鐘
クライトンは医学博士号を持ち、ハーバード医科大学で学んだ経歴がある。彼は科学の進歩が人類に大きな影響を及ぼす一方で、それを制御する倫理的判断が欠如していることに危機感を持っていた。この懸念は『ジュラシック・パーク』において明確に示されている。
「科学者たちは“できるかどうか”ばかりを考えて、“やるべきかどうか”を考えない」 — イアン・マルコムのセリフ(原作より)(関連記事:「『ジュラシック・パーク』キャスト・登場人物まとめ|相関図つきで解説」)
このセリフは、クライトンの科学観や倫理観を象徴するものであり、物語全体を貫く思想として繰り返し描かれている。
『ウェストワールド』から続くテーマ
1973年にクライトンが監督・脚本を務めた映画『ウエストワールド』は、最新技術によって運営されるテーマパークが暴走するという内容だった。この作品ではアンドロイドが制御不能となり、パーク内で人間を襲い始める。
『ジュラシック・パーク』は、この構図を自然科学とバイオテクノロジーの領域に置き換えたものである。技術によって制御された空間が、いかに簡単に崩壊するかを描いている。
クライトンにとって、科学がもたらす利便性とそれに内在する危険性を描くことは、一貫した創作テーマであった。
まとめ:クライトンの問いは今でも有効か?
『ジュラシック・パーク』が発表された1990年代と比べて、現代の科学技術はさらに高度化している。遺伝子操作、人工知能、合成生物学など、クライトンが描いたテーマは今も現実の課題となっている。恐竜を蘇らせるという物語はフィクションであるが、「人間が技術をどう扱うべきか」という根本的な問いは今も変わっていない。
その意味で、『ジュラシック・パーク』は単なる娯楽作品ではなく、科学と倫理の問題を提起する作品として読み継がれる価値を持っている。