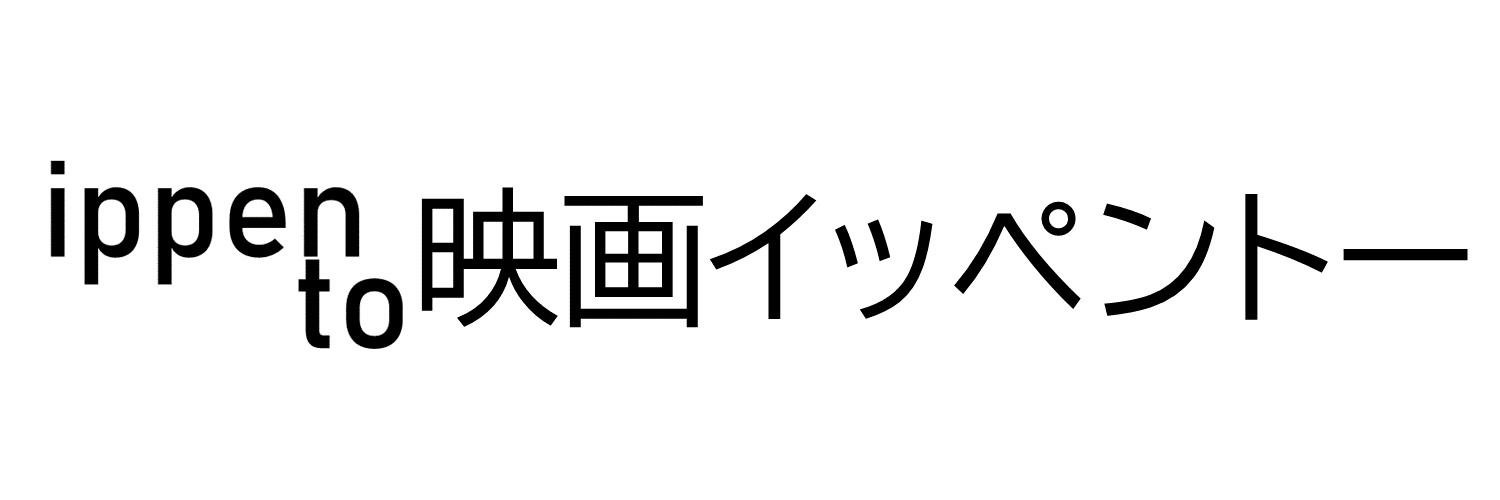1993年に公開された映画『ジュラシック・パーク』は、観客を「生きている恐竜」の存在に震撼させ、VFXの歴史に大きな転換点をもたらした。当時SFX(特殊撮影)が全盛だったハリウッドにデジタル革命をもたらし、その後の映画製作に多大な影響を与えた。
費用とリアリティの追求:アナログからデジタルへの道のり
スティーブン・スピルバーグ監督は当初、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドのアトラクション「キングコング・エンカウンター」を手がけたボブ・ガーとともに、すべての恐竜を実物大で製作することを望んでいた。キングコングのリアルな動きと毛皮の下に見える筋肉の表現に感銘を受けたためだ。しかし、これは費用的に現実的ではないと判断され、ハリウッドのトップクラスの特殊効果の才能が集結し、デザインチームが構成された。そのメンバーは、スタン・ウィンストン、フィル・ティペット、デニス・ミューレン、マイケル・ランティエリといった錚々たる顔ぶれだった。
アナログなプリビジュアライゼーションと科学的監修
Image: Making The Dinosaurs | Jurassic Park Documentary (1993) | Screen Bites – YouTube フィル・ティペットのミニチュアによって、スピルバーグ監督の絵コンテは忠実に再現された。
恐竜を映像に再現する最初のステップとして、粘土で作られた小さな恐竜のモデルが使用された 。フィル・ティペットは、スピルバーグ監督の絵コンテを3次元的に再現し、動きをつけて一時的な映像シーケンスを作成した 。これは現在「プリビジュアライゼーション」と呼ばれる工程のアナログ版であり、撮影現場で俳優たちに恐竜の動きを具体的に示すためのテンプレートとして活用された 。
スピルバーグ監督は、恐竜をモンスターとしてではなく、あくまでリアルな動物として描くことに強くこだわった 。そのため、世界有数の恐竜専門家である古生物学者ジャック・ホーナーの協力を得て、徹底的なフィールドワークを行い、科学的に正確な恐竜の行動描写を追求した 。ホーナーの研究は、当時の「恐竜は爬虫類に近い」という通説を覆し、「鳥類に最も近い生き物である」という最新の視点を取り入れる上で重要な役割を果たした 。
例えば、当初フィル・ティペットが作成したラプトルのプリビズでは、爬虫類のように舌を出す表現があったが、ホーナーはこの科学的な誤りを指摘し、修正を指示している 。この徹底した科学的監修が、恐竜たちのリアリティを底上げした 。
ゴー・モーションからCGIへの転換
Image: Making The Dinosaurs | Jurassic Park Documentary (1993) | Screen Bites – YouTube スピルバーグ監督へのデモのために作成された野原をかける骨格だけのガリミムスの群れ
初期の計画では、広範囲のショットはフィル・ティペットが完成させた「ゴー・モーション」という技術で撮影する予定だった。これは伝統的なストップモーション・アニメーションにモーションブラーを加えてより現実に近づけたもので、素晴らしい成果を上げていた。しかし、スピルバーグ監督は、自分の子供たちが「本物の恐竜だ」と信じる一方で、彼自身はまだ動きのぎこちなさを感じていた。
そこでデニス・ミューレンは、コンピュータ技術(CGI)の可能性を提案する。それまでILM(インダストリアル・ライト&マジック)は、『ターミネーター2』の液体金属のT-1000など、様式化されたクリーチャーは制作してきたが、生き物に命を吹き込むことは新たな挑戦だった。
最初のテストは、骨格だけのガリミムスの群れが走る映像だった。この映像を見たスピルバーグ監督は心を奪われ、コンピュータでフルサイズの恐竜を再現できる可能性を確信する。そして、肉付けされたティラノサウルスがガリミムスを追いかけるCGI映像をスピルバーグ監督とともに初めて見たフィル・ティペットの口からは、映画本編にも登場する有名なセリフ「I think I’m extinct.(絶滅したと思う)」が飛び出した。これは、自身の得意とするゴー・モーション技術がCGIに置き換わるという衝撃と、CGIの可能性への驚きを表していた。
ILMの技術者たちの挑戦と「恐竜になる」ワークショップ
CGIへの移行は決定的だったが、大きな課題があった。それは、コンピュータ上でどのように恐竜をリアルに動かすかということ。ILMの共同視覚効果スーパーバイザーであるマーク・ディッペは、それまで様式化されたクリーチャーを手がけてきたILMにとって、生き物を作ることは「本当の挑戦だった」と語っている。
アニメーターたちはコンピューターの前を離れ、パントマイムの指導を受けた。自分の体の動きを意識し、どのように動いているのか、足の運び方までを深く理解するトレーニング。これは、恐竜のリアルな動きをCGIで再現するために不可欠な要素だった。
さらに、アニメーターたちは実際に「恐竜になりきる」ワークショップも行った。倒れた大木に見立てたパイプの上を走り飛び越える訓練や、ガリミムスやティラノサウルスになったつもりで走り回り、狩りをする様子を撮影し、動物の動きのイメージを掴んでいった。
独自のツール開発と動物の動きの参照
Image: Making The Dinosaurs | Jurassic Park Documentary (1993) | Screen Bites – YouTube ティペット・スタジオが作成した「恐竜入力デバイス(DIT)」
フィル・ティペットのスタジオでは、伝統的なストップモーション・アニメーションの技術を現代のコンピュータ・アニメーションに応用する方法も模索された。アニメーターたちが慣れ親しんだミニチュアを実際に動かすことで、その動きがそのままコンピュータに反映される「恐竜入力デバイス(DIT)」というニックネームのハードウェアが開発された。これにより、キーボード操作ではなく、直感的な動きでCGIの恐竜をアニメーションさせることが可能になり、リアルな動きの再現に貢献した。
恐竜の最終的な動きは、既存の動物たちを参考にしている。ブラキオサウルスはキリン 、ガリミムスの走りはダチョウ 、ティラノサウルスは象の動きが参考にされ、その重量感やリアリティが追求された。これにより、空想上の生き物ではなく、実際に存在する動物のように見える恐竜がスクリーンに誕生した。
芸術・科学・技術の融合
スティーブン・スピルバーグ監督は、本作を「特殊効果と芸術性と科学と古生物学の素晴らしいコラボレーションだった」と振り返っている。ILMのVFXスーパーバイザーであるマーク・ディッペやランダル・デュトラは、技術の進歩は素晴らしいが、最も大切なのは「ストーリーテリング」であり、「テクノロジーは、ストーリーをサポートするツールであるべき」だと強調している。
参考資料:
- Making The Dinosaurs | Jurassic Park Documentary (1993) | Screen Bites – YouTube 2025年9月21日閲覧
- [鍋潤太郎のハリウッドVFX最前線]Vol.42 「ジュラシック・パーク」のスタッフが語る当時のVFXとは? – PRONEWS : 動画制作のあらゆる情報が集まるトータルガイド 2025年9月21日閲覧