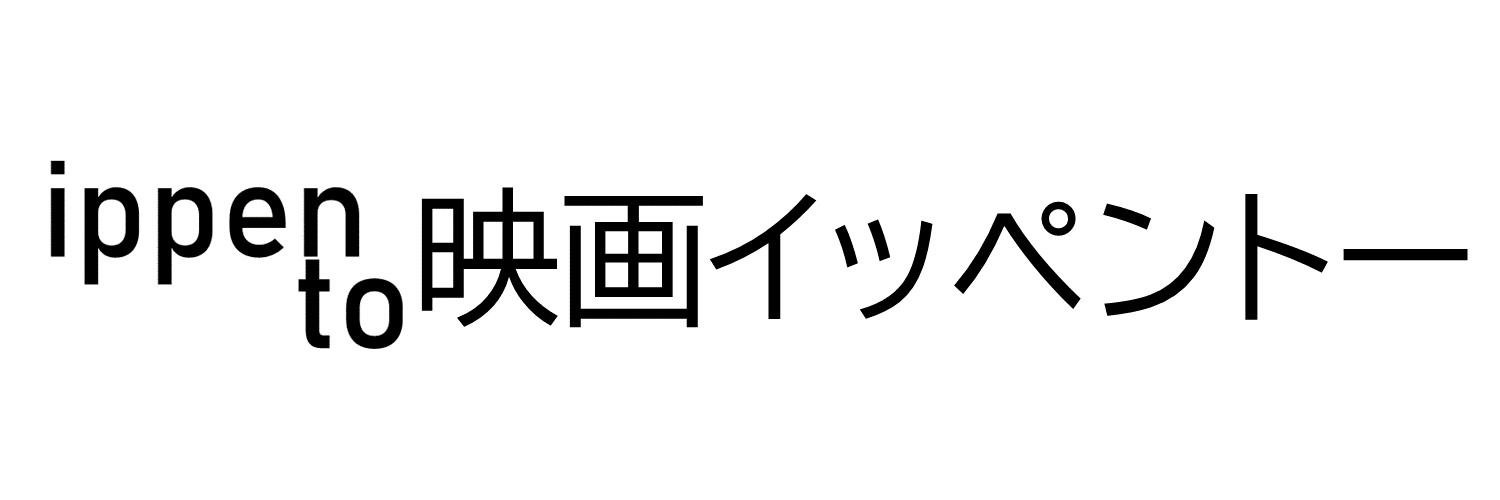観終えた後に、ただ「面白かった」では片付けられない、重く、そして鮮烈な役者人生を突きつけられる映画『国宝』。絶賛の声が上がる一方で、一部では「正直つまらない」「見ていて疲れた」という戸惑いの声もある。
なぜ、これほどまでに評価が分かれるのだろうか?
その答えは、本作が一般的な映画の「お約束」をあえて裏切り、人間関係のカタルシスではなく、一人の役者が芸の頂点に至るまでの壮絶な孤独と、その果てに見る「景色」そのものを描くことに全てを捧げているからだ。
この記事では、鑑賞前の方向けのキャストやあらすじといった基本情報を押さえつつ、なぜこの映画が「楽しくない」と感じられるのか、その構造的な理由を徹底的に解き明かしていく。そして、登場人物たちの不可解に見える行動の真意、物語の核心であるラストシーンの意味まで、あらゆる疑問を考察していく。
映画『国宝』の基本情報(キャスト・あらすじ等)
作品概要
原作者吉田 修一自身が3年間歌舞伎の黒衣を纏い、楽屋に入った経験から書き上げられた「国宝」。監督はフラダンスで町おこしをする人間模様を描いた『フラガール』(2006)の 李相日。
また『アデル、ブルーは熱い色』(2013)のソフィアン・エル・ファニが撮影、『キル・ビル』(2003)の種田陽平が美術監督として参加。
主題歌は音楽を担当した原摩利彦が手掛け、坂本美雨による主人公立花喜久雄の芸だけを追い求める人生を表すような歌詞をKing Gnu井口 理が繊細に歌い上げている。
175分、約3時間の本編では立花喜久雄の歌舞伎役者としてただひたすらに日本一を目指す姿が描かれている。映画は2025年6月6日公開。
あらすじ
雪が舞うなか、任侠の世界で一大勢力をなす立花組の新年会が行われていた。長崎での興行を行う挨拶のため、新年会へ顔を出す上方歌舞伎の名門の当主、花井半二郎。そこで目にしたのは素人の余興でありながらも、あまりにも美しすぎる女形を演じる立花の息子、立花喜久雄だった。その後組同士の抗争で親を失った喜久雄は半二郎に拾われ、その半二郎の息子、俊介とともに歌舞伎役者としての芸を磨いていくこととなる。
主要キャスト・登場人物一覧
| 役名 | 俳優名 | キャラクター概要 |
| 立花喜久雄 | 吉沢亮 黒川想矢(少年期) | 任侠の家に生まれるも、芸の道にすべてを捧げる主人公。 |
| 俊介 | 横浜流星 越山敬達(少年期) | 喜久雄のライバルであり、親友。花井の血を引く御曹司。 |
| 花井半二郎 | 渡辺謙 | 喜久雄を拾い、芸の道へと導く上方歌舞伎の名門の当主。 |
| 大垣幸子 | 寺島しのぶ | 半二郎を支える女将。喜久雄たちの母親的存在。 |
| 小野川万菊 | 田中泯 | 人間国宝の歌舞伎役者。喜久雄の芸に生涯影響を与える。 |
| 福田春江 | 高畑充希 | 喜久雄を幼い頃から慕い、彼の後を追う女性。 |
| 藤駒 | 見上愛 | 喜久雄の才能をいち早く見抜く、花街の芸妓。 |
| 彰子 | 森七菜 | 喜久雄の人生に深く関わることになる女性。 |
【ネタバレ考察】なぜ『国宝』は「楽しくない」のか?その3つの理由
本作はすさまじい映画ではあるが、「楽しい」とは言えず、むしろ「つらい」とまで感じるかもしれない。それはなぜか。この作風について、李相日監督自身が次のように語っている。
歌舞伎自体が古典芸能ですし、人間の業を炙り出すような、ドロドロとした内容の演目も多くあります。そういった普遍的な歌舞伎と、メロドラマ──この映画の基本のスタイルはメロドラマだと思いますが、その二つは極めて親和性が高い。
出典:【単独インタビュー】『国宝』主演・吉沢亮と李相日監督がカンヌで語った、“役者人生と人間の業” | Fan’s Voice | ファンズボイス 2025年7月11日閲覧
監督が言うように、本作の基本スタイルは、愛憎や過酷な運命を描く「メロドラマ」。だからこそ、私たちは立花喜久雄という一人の人間が、芸の道を究めるために払った犠牲の物語に、一切の美化がない「つらさ」を感じてしまう。
その「つらさ」の正体を、3つの理由から解き明かしていく。
理由1:人間関係の「達成感」が、意図的に描かれていない
喜久雄の人生には、春江、俊介、藤駒、彰子といった重要な他者が登場する。しかし、通常の物語ならば描かれるであろう恋愛の成就や友情の回復といった「達成感」は、ことごとく裏切られる。春江は俊介を選び、藤駒との間には子どもが生まれても家庭は築かれない。そして、どん底の彼を支えた彰子さえも、芸しか見えない喜久雄のもとを去っていく。「悪魔との契約」を願うほどの芸への渇望は、他者の介在を許さないのだ。
理由2:登場人物の行動に「共感」するのが難しい
喜久雄を裏切る春江の行動は、一見すると「ひどい」と感じられるかもしれない。しかし、これは彼女が単に心変わりしたのではない。芸の怪物となっていく喜久雄の世界に、自分の居場所が完全になくなったことへの悲しい決別なのだ。観客が感情移入しやすい「恋愛の論理」ではなく、芸の求道者に対する「凡人の論理」で彼女たちは行動するため、私たちは簡単に共感できず、突き放されたような感覚に陥る。
理由3:芸の道の「非情さ」が、美化されず描かれる
喜久雄の出自である任侠の世界や、歌舞伎界の凄まじい稽古、そして嫉妬や裏切り。本作は、芸の道の輝かしい部分だけでなく、その裏にある暴力性や非情さを容赦なく描く。特に、酔客に絡まれ打ちのめされるシーンなどは、主人公が輝く姿を期待する観客の心を直接的に痛めつけ、「つらい」と感じさせる要因となっている。
【ネタバレ解説】物語の真の輝きとラストシーンが示す「景色」
人間関係の「達成感」を徹底的に排したこの物語だが、では輝きはどこにあるのか。それは、前章で述べた「つらさ」の先、すべてを犠牲にした喜久雄が「芸」そのものと一体になる瞬間にこそ存在する。
芸で繋がる、俊介との「友情」
人生のすべてだった歌舞伎の舞台と春江を奪われ、憎しみ合ったはずの俊介。しかし、二人が同じ舞台に立ち、芸で対峙する時、そこには言葉を超えた魂の対話が生まれる。観客が見るのは、失われた人間関係の回復ではなく、芸の高みでのみ通じ合える、役者同士の絆という全く別の形の「友情」だ。
絶望を貫く、万菊の「言葉」
落ち目となり、歌舞伎への憎しみさえ抱いていた喜久雄に、人間国宝・万菊は「あなた歌舞伎が憎くて仕方ないんでしょう。でもそれでいいの、それでもやるの」と告げる。これは単なる激励ではない。芸の魔力に取り憑かれた者だけが理解できる、呪いであり、そして救いの言葉だ。この言葉で喜久雄は自身の置かれた立場を直視しながらも、どんな舞台だろうと歌舞伎役者としての道をあきらめることはなかった。
ラストシーン:ついにたどり着いた「景色」
そして物語の最後に、喜久雄は観客として見たあの万菊の「景色」を、今度は舞台の上から自身の目で見る。「きれいやなぁ」という呟き。これは、彼が人生を賭して追い求めてきたものの答えだ。愛する人々も、穏やかな日常も、すべてを失った果てにようやくたどり着いた、孤高の者だけが見ることを許される芸の頂点。その美しさと壮絶さこそが、この映画の真の輝きなのである。
まとめ:立花喜久雄の人生としての物語がただそこにある
映画『国宝』は決して楽しいと感じる映画ではないかもしれない。女形として生まれ持っての才能があり、当代きっての歌舞伎役者にも認められながらも結局は血筋という伝統に翻弄される壮絶な人生。しかし歌舞伎役者として芸を究め続けた立花喜久雄の物語がただそこにあると感じる。